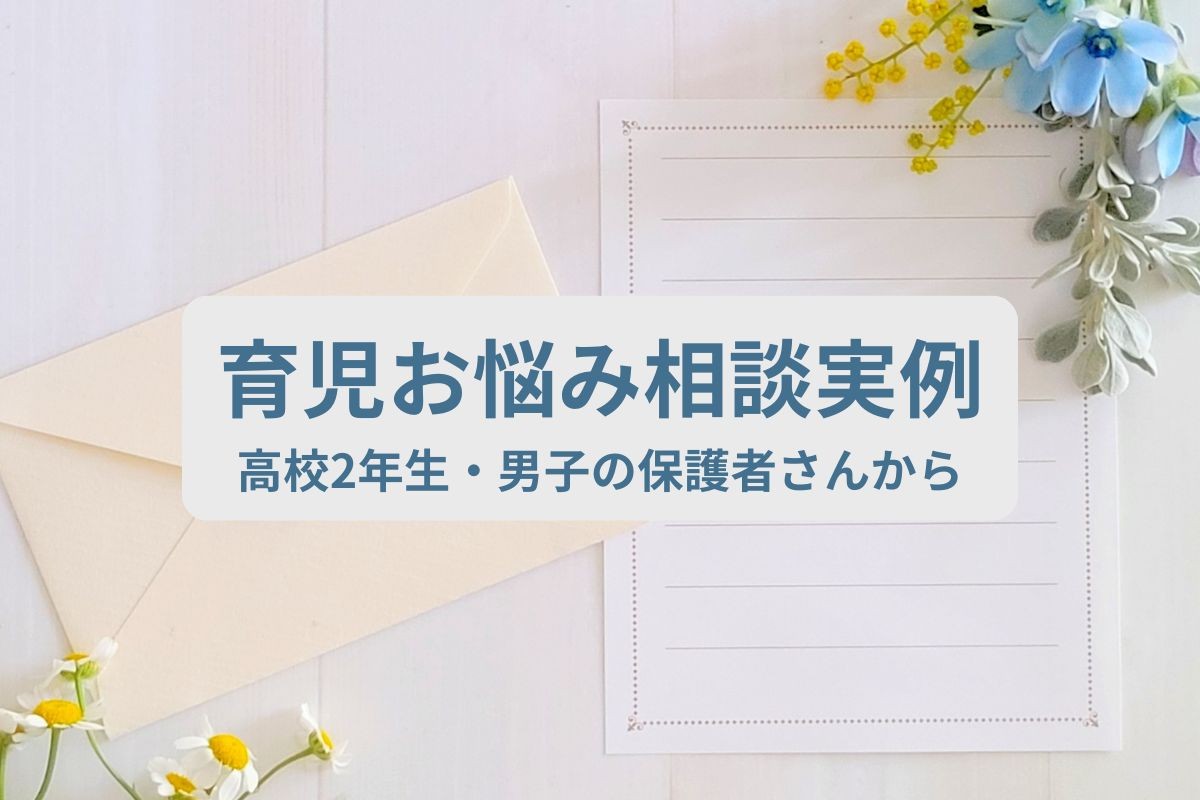高校2年生男子が不登校に。病気?それともほかに原因が?【本当にあった育児相談Q&A】


5月に多い「不登校」の相談。今回は男子高校生の保護者さんから寄せられた相談への回答
みなさんこんにちは。レインディアの藤原です。
5月は過ごしやすくなってDIY好きの私は、この1年保留していた作業を詰め込んで過ごしています。
お店の外壁塗装や作業場の整理整頓、畑仕事や工具の手入れ、そして子ども部屋の整理整頓。やっぱり親がお手本を見せないと、子どもは片付けられませんよね。
物にあふれる現代。娘の部屋にはカプセルトイや何かの景品、おもちゃで足の踏み場もありません・・・。久々に発掘されたおもちゃで遊び、時間をムダにしたり、部品がなくて探すだけで疲れたり。でも、キレイになった後は気分もスッキリ。充実感を味わえます。
一方、新生活が始まって緊張感がゆるむころ。「五月病」の言葉が出てくるこの時期は、不登校や育児相談が立て続けに寄せられます。
そこで今回のコラムでは、この4月に実際に受けた相談を例に、この時期に考えて欲しい対処法の一例をご紹介。
〜相談内容〜
(相談者:高校2年生・男子の保護者さんから)
高校1年生の時は楽しく学校に行っていたのですが、2年生になってすぐから行き渋りが始まり、最近は吐き気や身体の不調を訴えずっと休んでいます。
本人によると「部活に上手な後輩が入ってきて自信を失った」と言うのですが、どうしたら良いでしょうか?
病院に行って見てもらったところ、起立性調節障害の可能性を言われ、血圧上昇の薬や漢方を考えています。
不登校=病気と早合点する前に、まずは子どもの話に耳を傾けて
このお母さんは、私へ相談される前に、すでにスクールカウンセラーや精神科病院にも相談されていました。
全国的に心療内科や精神科の予約すら取りづらい現状。不登校を「病気」と位置づける世論の流れに、私は個人的に疑問を抱いています。
もちろん、医療的支援が必要なケースもあります。しかし、保護者や子ども本人の話を、2~3時間じっくり聴くだけで改善や復学へとつなげていることも多い私としては、複雑な思い。
子どもが「辛い」、「苦しい」、「痛い」、「どうにかして欲しい」と言葉で訴えてくるのであれば、医療機関への相談は有効な手段。
けれど、「学校に行きたくない」、「休みたい」、「身体が動かない」、「朝起きられない」といった訴えの場合、親が不安になり早合点すると、不登校が長期化する要因に。
子どもが登校を渋った時に、最初に大切にすべきは「子どもの言葉」。
私自身が不登校になった際、もっとも辛かったのは、親が私の言葉を無視し、病院や宗教などの専門家に相談していたこと。
子どもが登校を渋った時、親はどう声をかければいいか分からず、結果、間違った言葉で子どもを追い詰めてしまうことも。父親は「甘えるな!」などと叱り、力づくで登校を促す。母親は「私の育児が間違っていたのか?」、「学校に問題があるのでは」と混乱し、右往左往。
学校の先生は、「何か悩みがあるなら話して欲しい」、「いじめなどの問題があるなら相談に乗る」と、原因を探そうとするでしょう。
こうした行動をとる保護者に対して、私は「その態度はすべて間違っている」とお伝えしています。
理由はただひとつ。子どもからすれば「親に信頼されていない」と感じてしまうからです。
高校生にもなれば、自分で問題を解決しようとし、自分の人生を自分で判断しようとします。
試行錯誤の中で上手くいかない時には、子どもの方から相談を持ちかけてくるハズ。大人の方が慌てて先手を打とうと行動するので、子どもからすると親や先生、大人に相談する気持ちがなくなってしまいます。
結果として、子どもが孤立。問題が解決へ向かわない悪循環。
大切なのは、「子どもが誰を信頼するか」。
実際の相談者と私のやり取りの一部をご紹介
では、ここからは、実際のやりとりを例に説明します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私:
新年度が始まり、寒暖差の影響もあって自律神経が不安定になりがちな時期。気圧の変化によって、大人でも偏頭痛や関節痛を感じることがあります。お子さんは、充分な睡眠を取れていますか?食事や運動の状況はいかがですか?
朝起きられない、確かに病気の可能性もありますが、単に睡眠不足かもしれません。気温の変化に対応するだけでも、体力を消耗しますからね。
ひとつ確認させてください。昨年の今ごろ、お子さんの体調はいかがだったか覚えておられますか?
現在高校2年生ということは、1年前は受験生。おそらく、これまでで一番ストレスのかかった時期だったと思います。
部活動が原因とお子さんは話されたようですが、それも理由のひとつかもしれません。ただ、それだけなら部活を休めば済む話。周りの大人に伝えるための分かりやすい理由、あるいは本人がそう思い込んでいる理由かもしれません。
実際には、不登校の原因を子ども自身が分かっていない、あるいは防衛本能によって忘れてしまっているケースも少なくありませんから。
↓↓↓
相談者:
昨年のことはよく覚えています。受験生でストレスが多く、花粉症もあり、薬を服用しながらの苦しい春でした。
今年は花粉症が軽く、先日、息子とも「今年の春は楽だね」と話したばかりです。
私:
私も花粉症ですが、今年が楽とは感じません。恐らく、昨年は勉強のストレスや生活リズムの乱れが体調に影響していたのでしょう。今年の不登校、行き渋りが始まったころの吐き気などは、もしかしたら昨年のトラウマがあるかもしれませんよ。
春になり、昨年と似た気温・湿度・匂い・学校の雰囲気。昨年の状況が急に蘇ってきて、不安に襲われた可能性はないでしょうか?
小学生のような低年齢の不登校では、1年前の出来事が原因とは考えづらいですが、高校生ともなると1年の感覚は短く、大人でも適応障害を診断された翌年に同じくメンタルが落ち込む話は多々あります。
つまり、今回うかがった内容からだけで考える限り、今回の不登校に具体的に解決可能な理由があるワケではなく、過去の新年度が始まる“不安”が原因ではないかと推測します。
もしそうであれば、お母さんがとるべき対応は「不安を増幅しないこと」。不安げな表情を見せれば、息子さんは罪悪感を感じるでしょうし、そんな母親を見たくなくて顔を合わさないようになるかも。
今、息子さんはどのような言葉を口にしていますか?「もう学校へは二度と行きたくない」と言っていますか?
↓↓↓
相談者:
「今はテスト期間だから、行くと“テストが嫌で休んだ”と思われる。それは嫌だから、テストが終わって少し日数をあけてから登校する」と言っています。
でも、本当に行けるのか心配。行かない期間が長くなれば、それだけ行きにくくなるのではないでしょうか?
私:
確かに、日数が空けば行きづらくなりますよね。けれど、息子さんの言葉をお母さんが信じないで、誰が信じるのですか?
今は、「子ども単体」で考えるのではなく、「お母さんと息子さんの関係性」を意識する段階。子どもを孤独にしないこと。もし学校に行けないとしても、息子さんの言葉を信じたのであれば、息子を守ったことになると思いますよ。
息子を子ども扱い、息子を病人扱いしたがゆえに、世の中ではどんどん不登校児童が増えています。息子を子ども扱い、病人扱い。こうした対応が、社会全体で不登校を増やしている要因。
ちょっとしたつまずきを、大ケガと判断して入院させるような事をしてはいけません。
今まで一生懸命育ててきた息子さんが、この壁を乗り越えられないと思いますか?
お母さんが不安な表情・行動を見せれば、息子さんは罪悪感を抱き、「学校に行かないこと」が大事だと思い込み、大きなプレッシャーとなってしまいます。
むしろ、「人生、疲れたら休むことも大事。しっかり休んで、さっさと次に行こう」と、前向きな態度を取ってみてください。
そうすれば、恐らくお子さんは気候の変化とともに、学校へも行くようになると思いますよ。
このお子さんは、その後学校に復帰、まだ遅刻したり時々休む事もあるようですが、頑張ってくれていると思います。
昨年は、小中高含め約40名ほどの不登校相談がありました。
学校に行かないという行動は、何らかのSOSの可能性があるので、そのサインをちゃんと見極めることが不登校克服の第一歩。
お名前や住所、連絡先などの個人情報は必要ありませんので、お気軽にご相談ください。
お悩み相談を受付中です
みなさまも何か聞いてみたい事などありましたら、お気軽にお悩み相談フォームにお寄せください。ただ、ここのところ方々から相談が数多く寄せられており、お返事にお時間をいただく場合があります事、ご了承ください。
-------
下記相談フォームより、匿名での無料相談も受付中。鳥取県外の方のご相談も大丈夫です。
なお、メールでの回答となりますので、私からの回答が迷惑メールフォルダに入っている場合があります。
また、順番に対応していますが、全国から相談が寄せられていますので、現在、お返事までに3~5日間程度の日数がかかる事をあらかじめご了承ください。
※掲載の情報は、記事公開時点の内容です。
状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、最新の情報は店舗・施設のHPやSNSを確認するか、直接お問い合わせください。
鳥取・島根のお仕事情報
この記事を書いた人

Reindeer 代表取締役社長
レインディア藤原さん
北欧インテリアショップ『reindeer』、木のおもちゃのレンタルプログラム「もくレン」などを運営。中海テレビ「県議熱中討論」コーディネーター、よなご宇沢会幹事も務める。幼稚園や保育園、市町村の子育て支援センターなどで育児講演を行う。乳幼児の育児相談から不登校問題もお気軽にどうぞ! いつも作りかけのお店はまさに秘密基地、まずは自分でするのが藤原流であり、北欧から学んだこと。お喋り大好きな二児の父です。
最近では、米子市岡成で子育て支援プロジェクト『コーセリ』の代表理事を務めています。私は子どもが生まれる前の妊娠期から、子育てや子どもの発達について学びながら準備をしていくことが、子育ての不安を減らすうえで大切と考えています。そのような視点から、子育て世代の親を対象としたセミナーを企画・開催しています。また、子どもと一緒に参加できる体験教室やイベントなども行っています。
【レインディア藤原さんの過去記事一覧はこちら】
コーセリプロジェクトHP